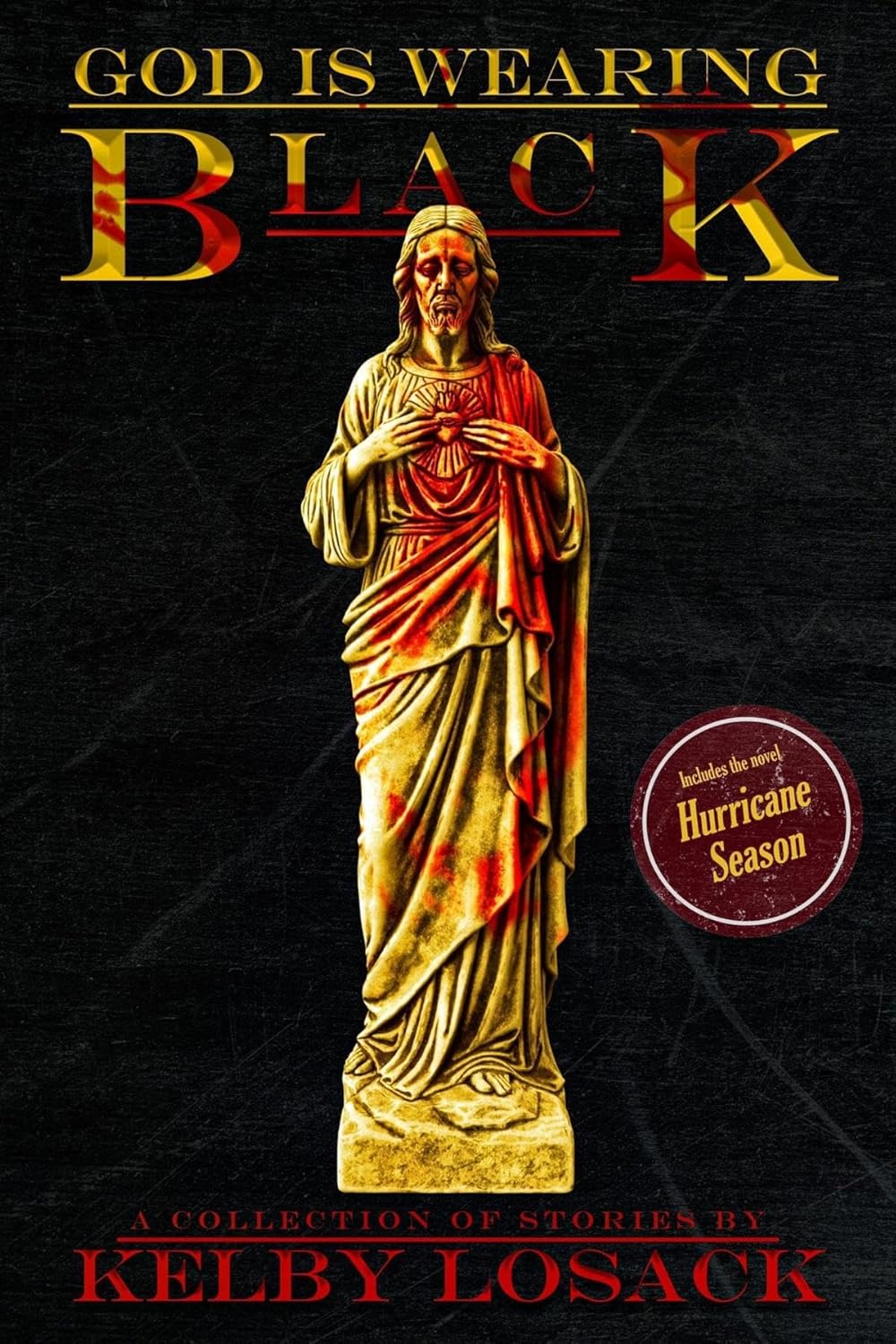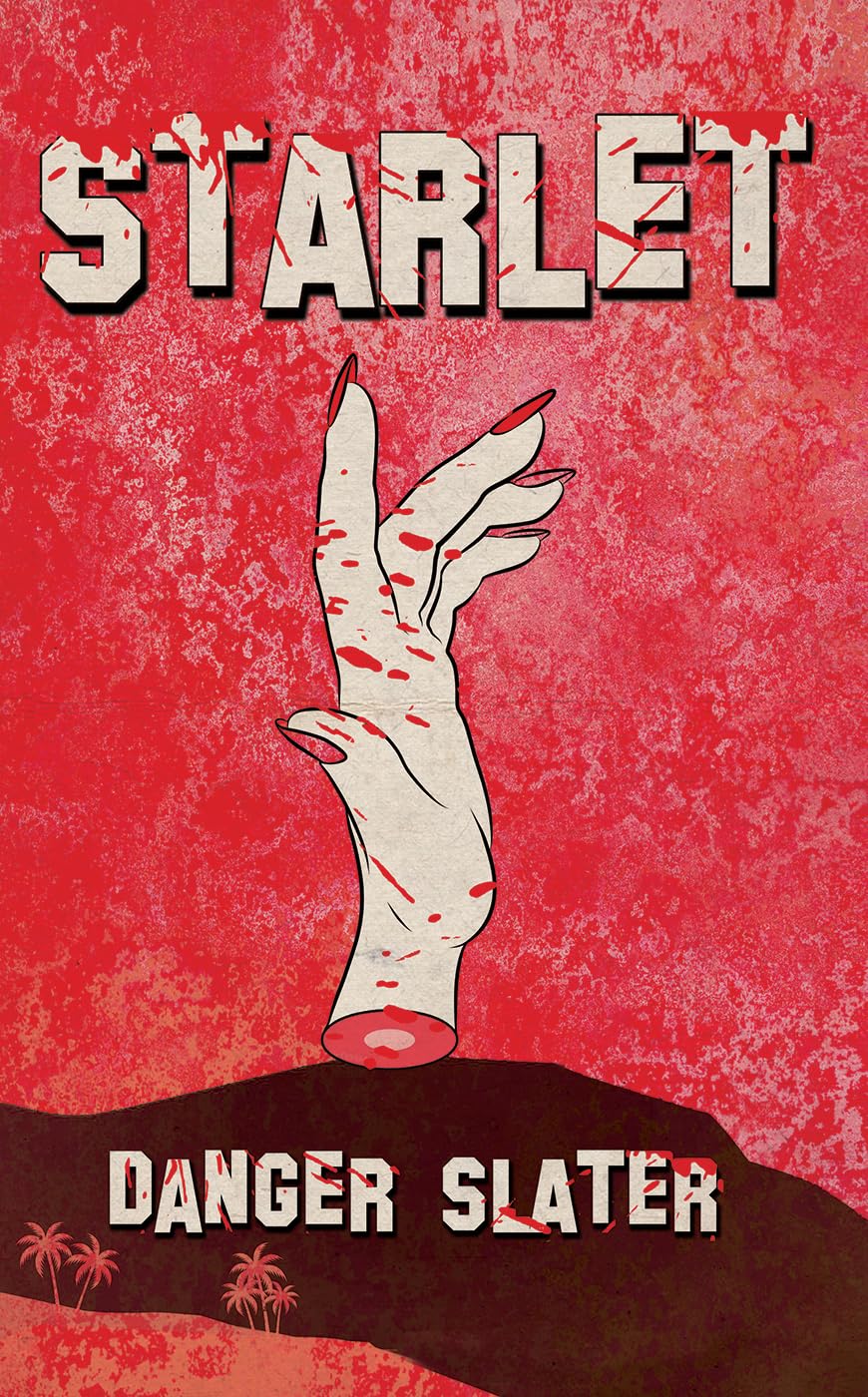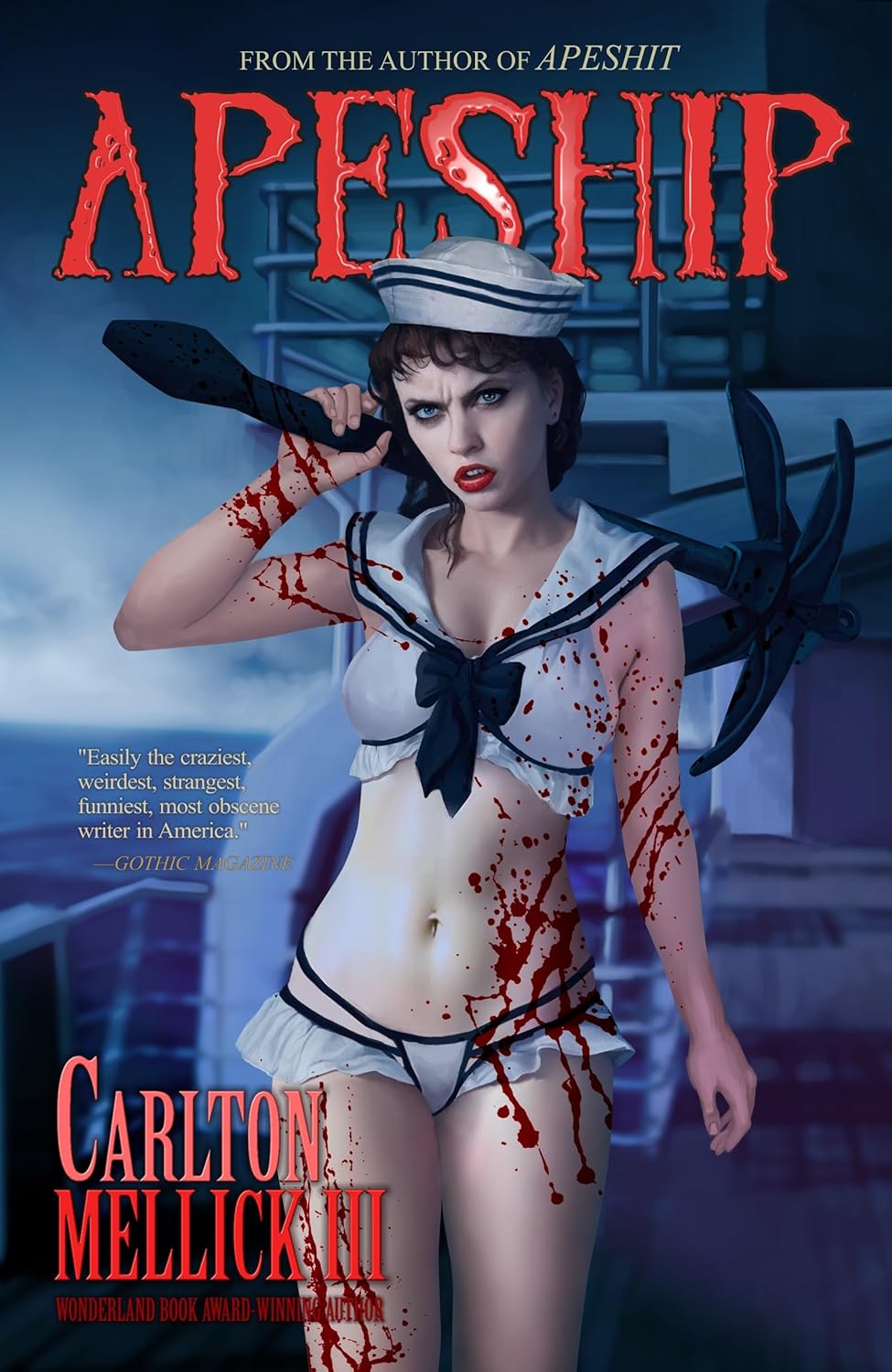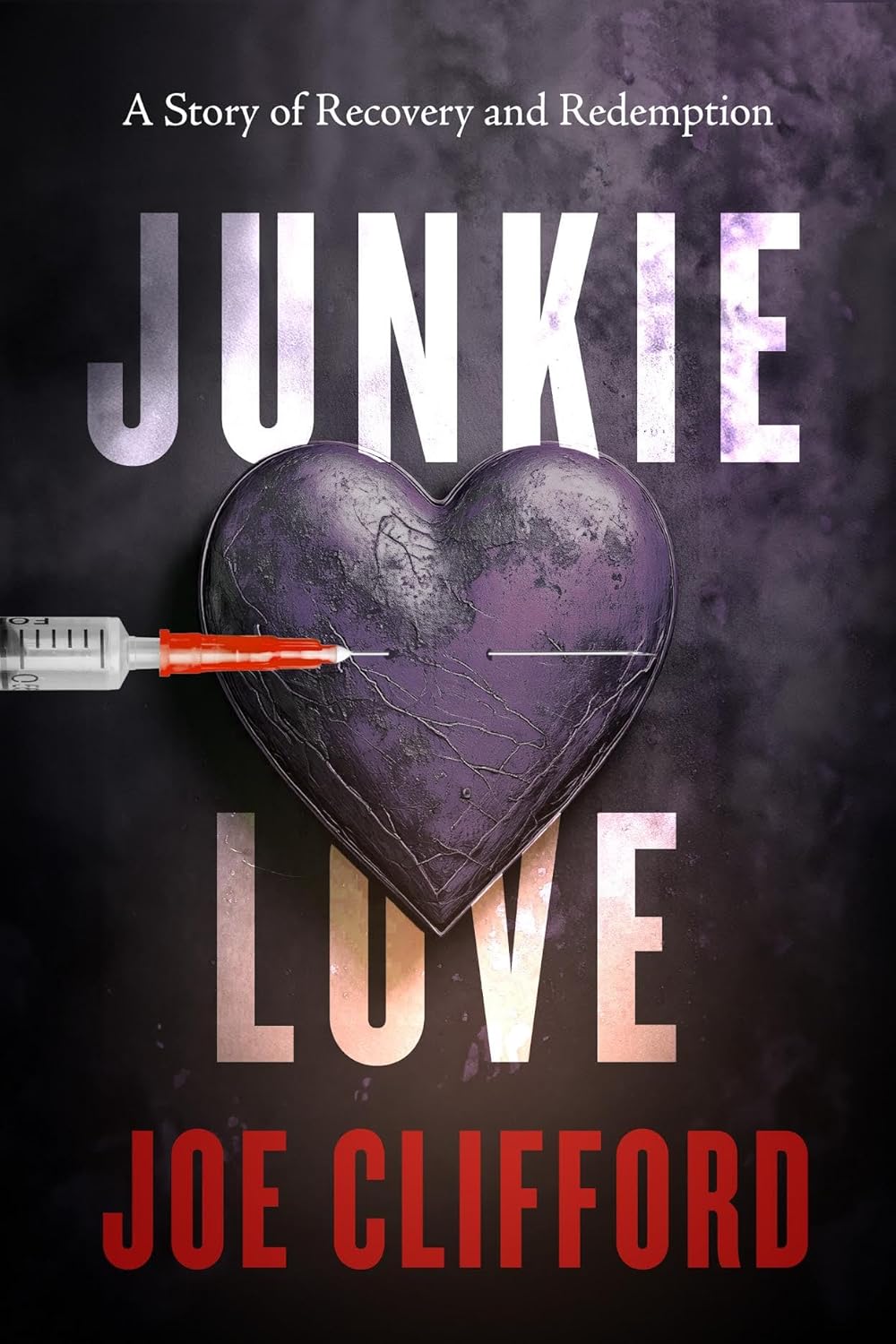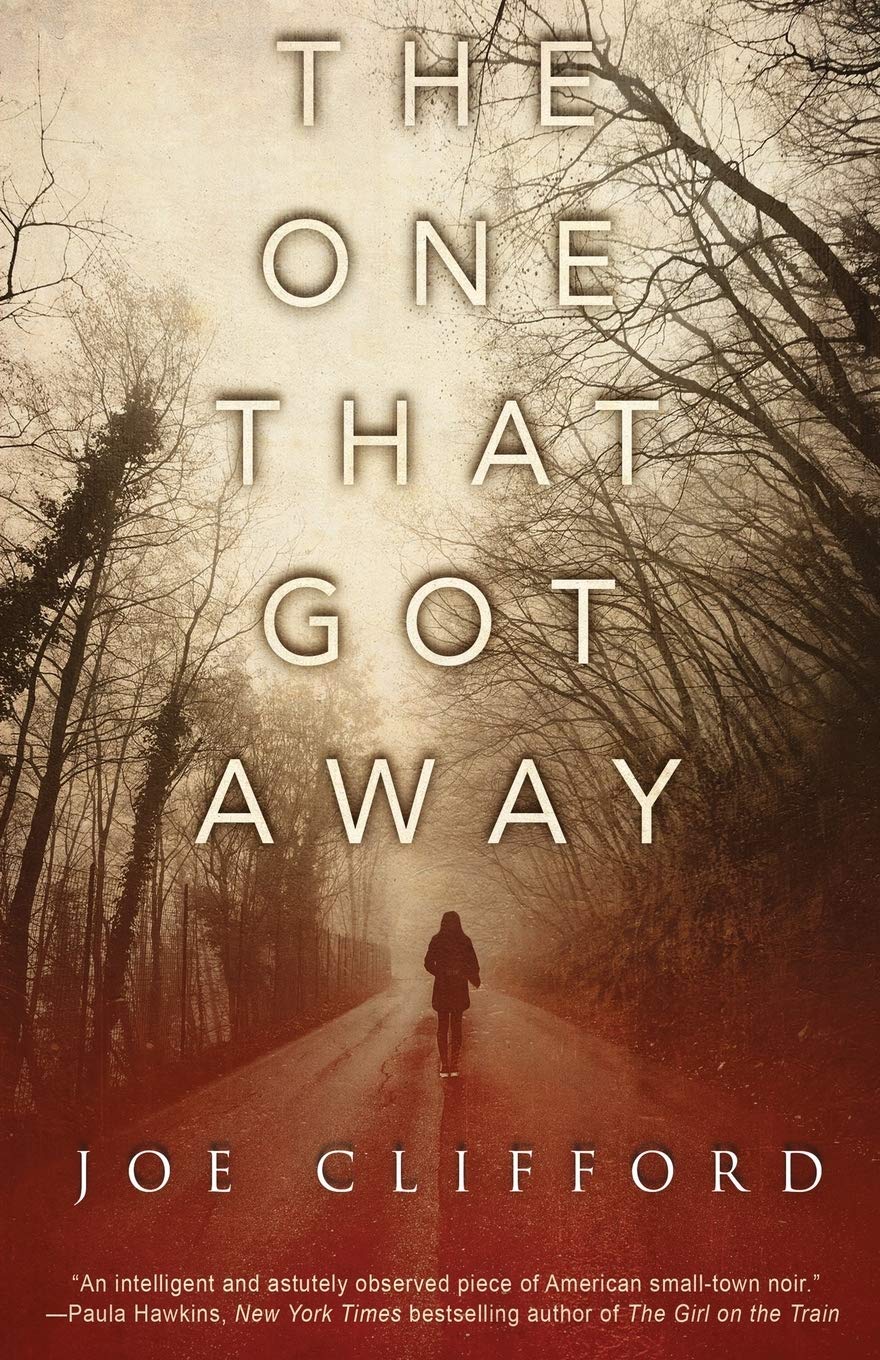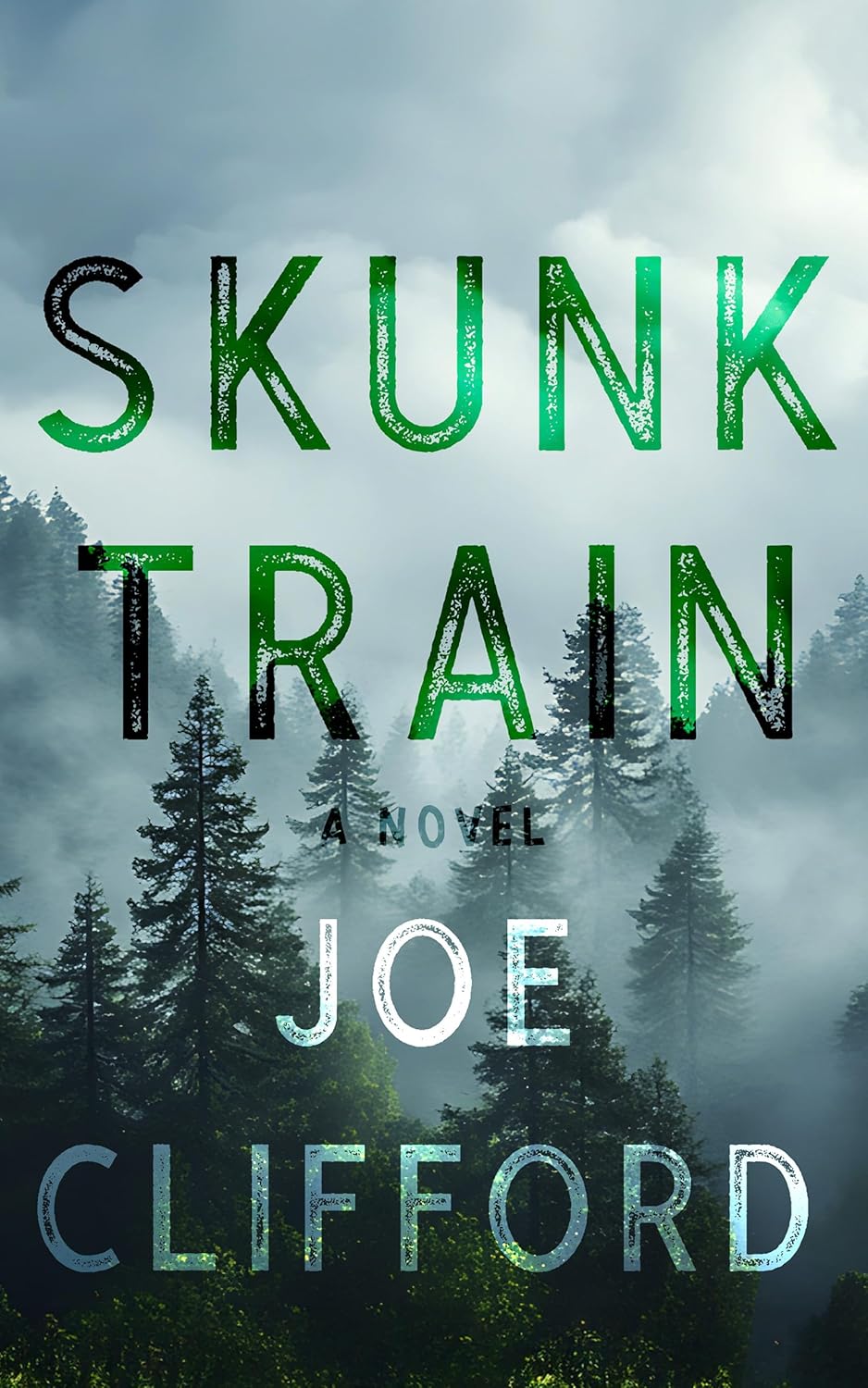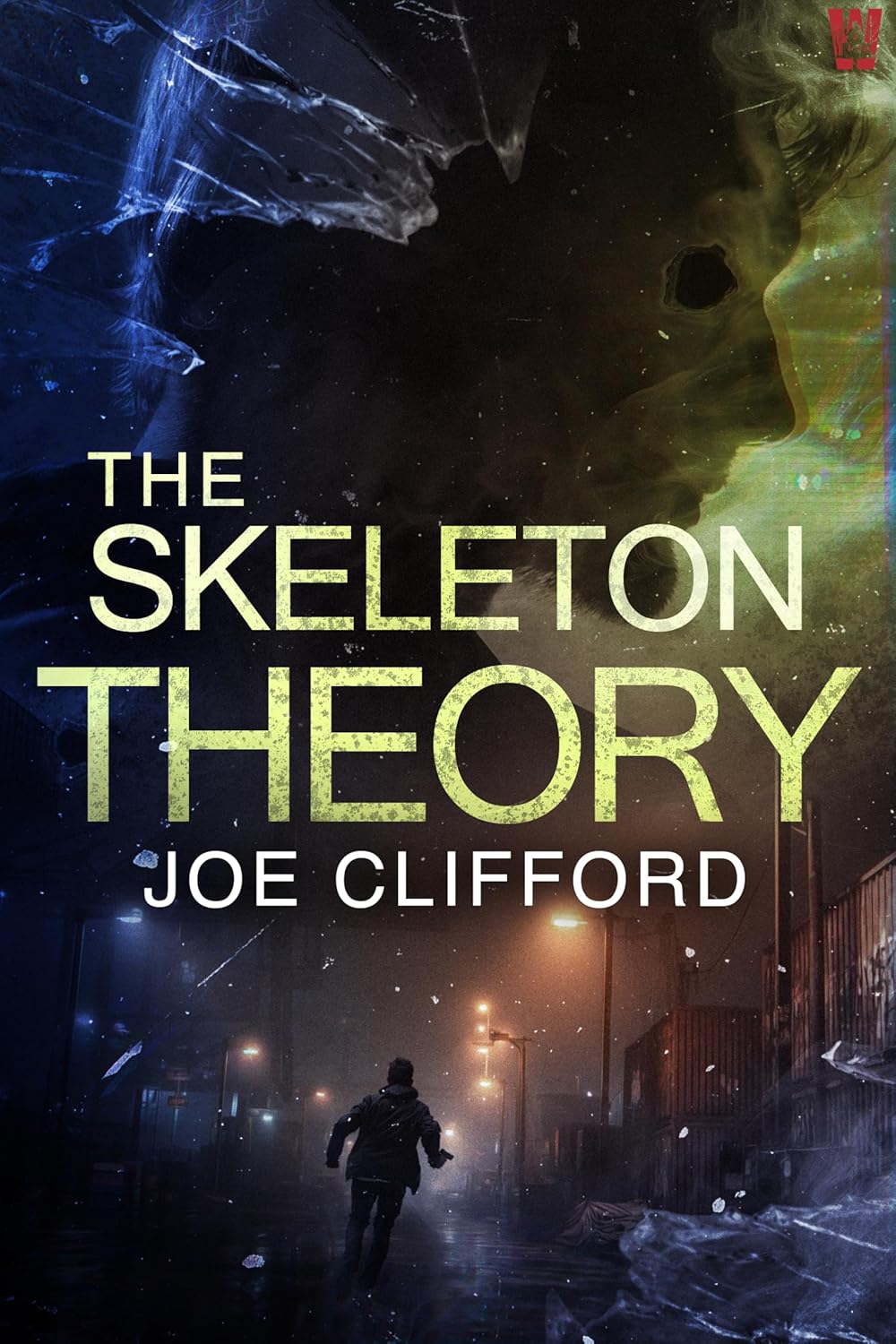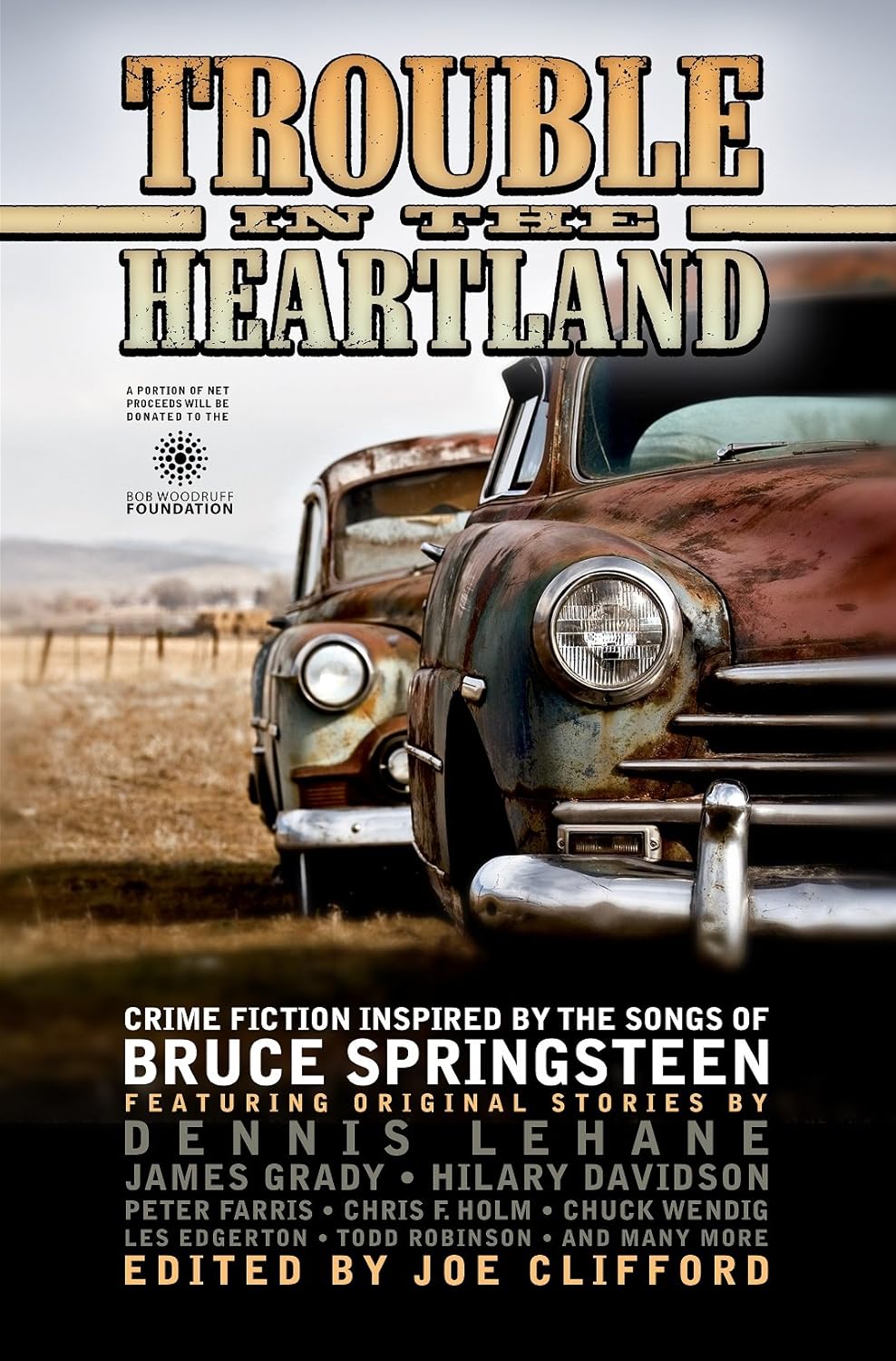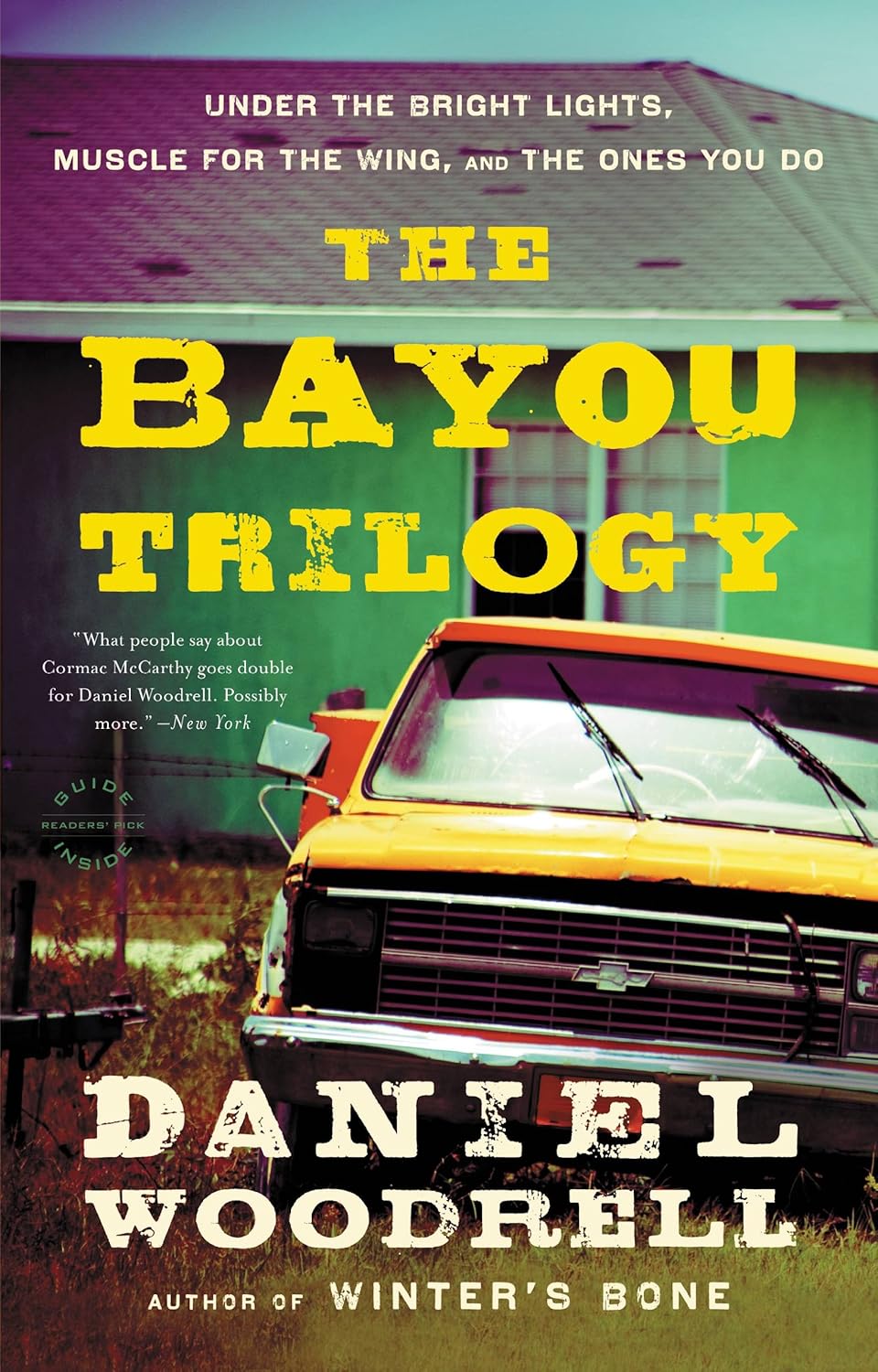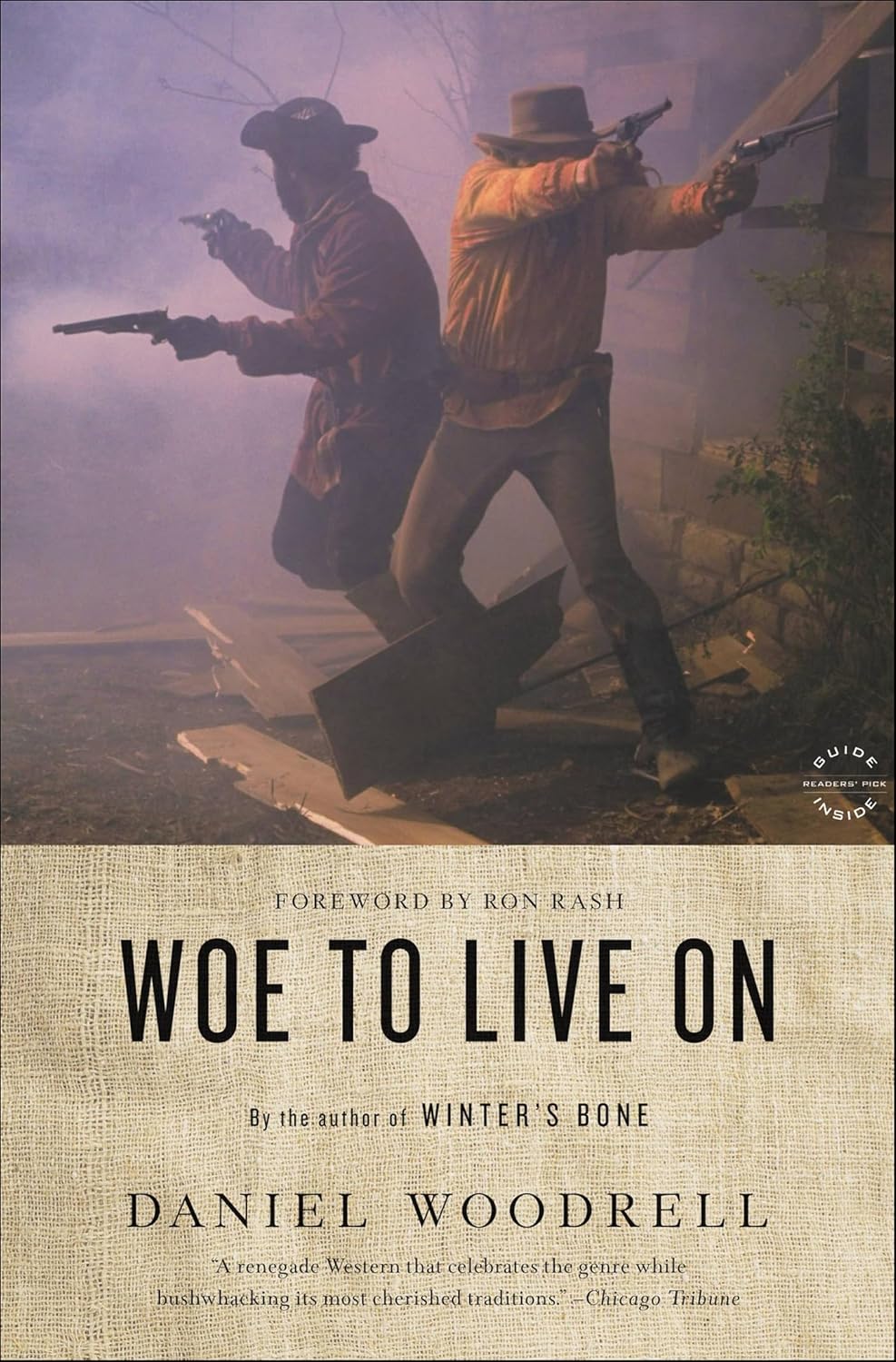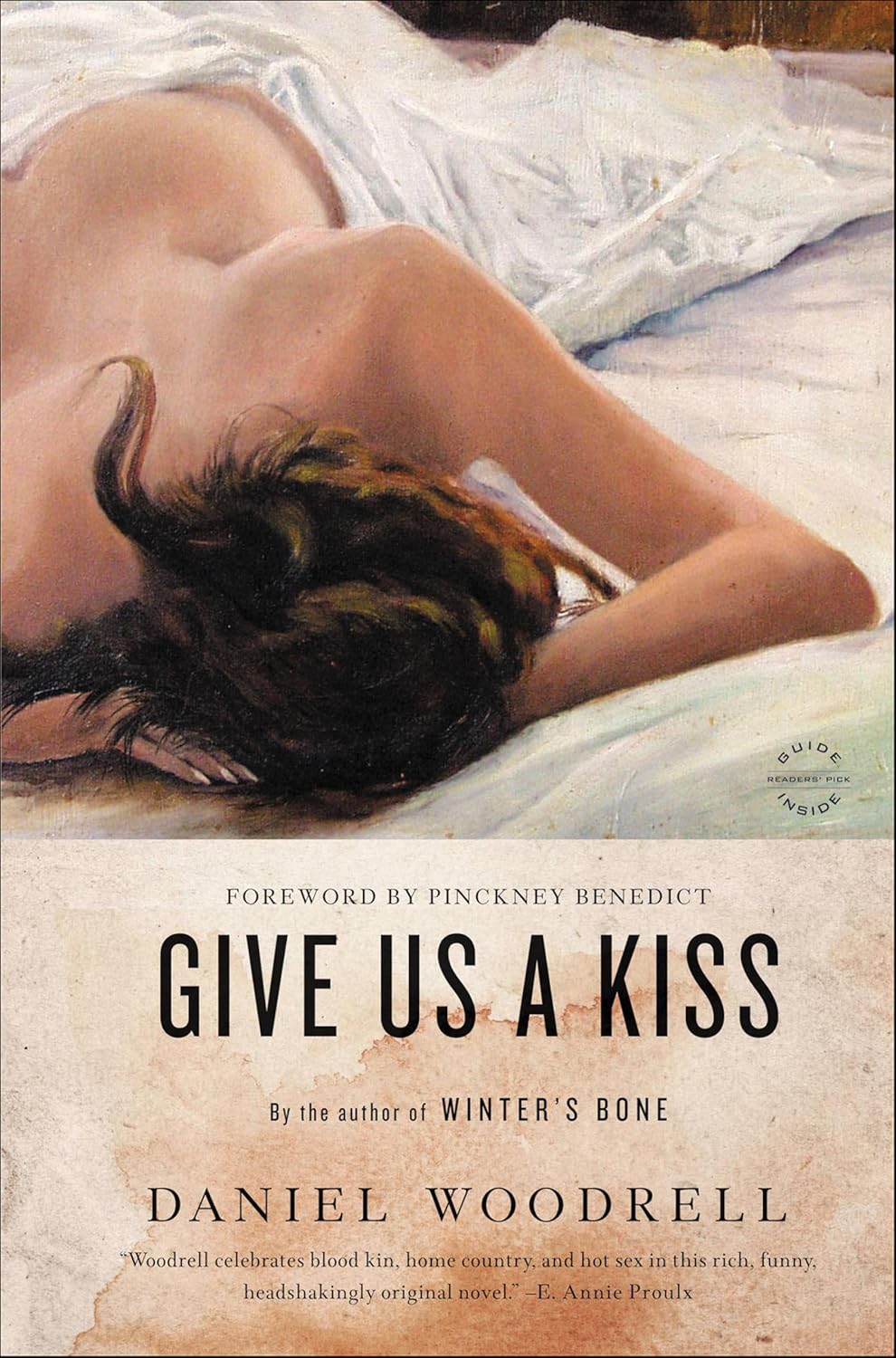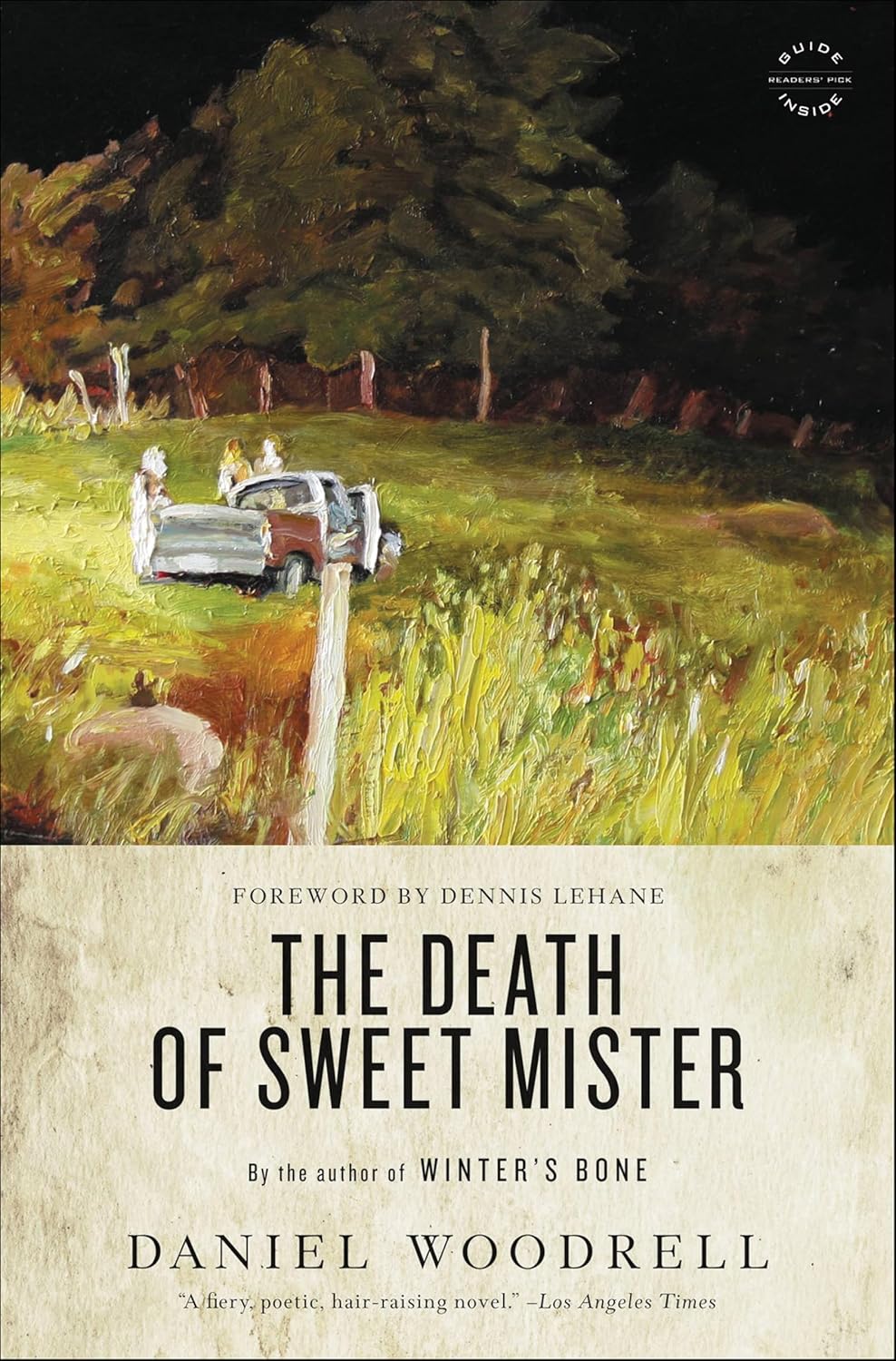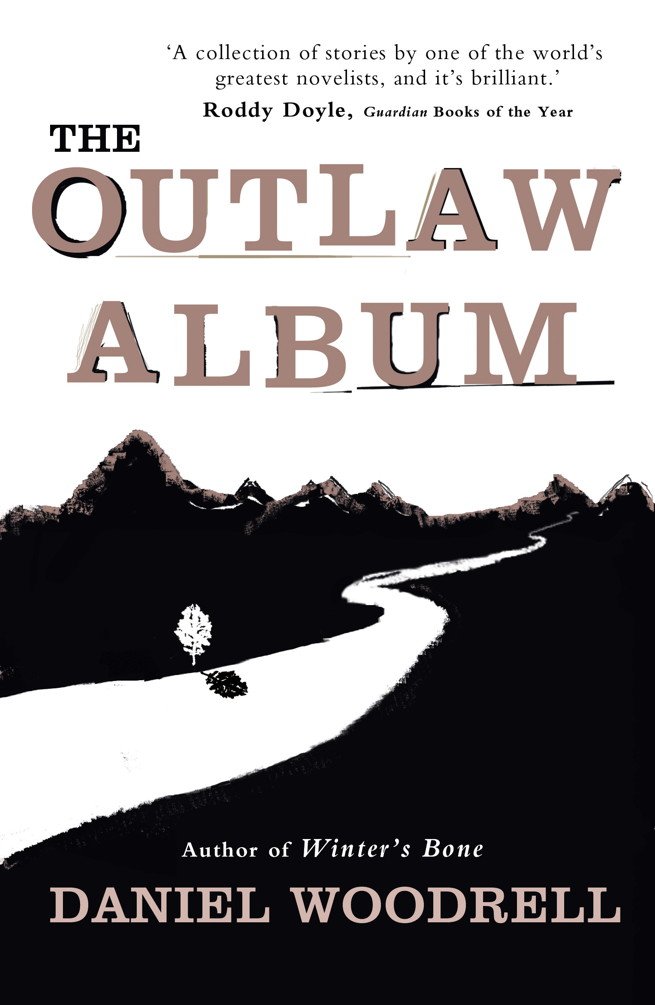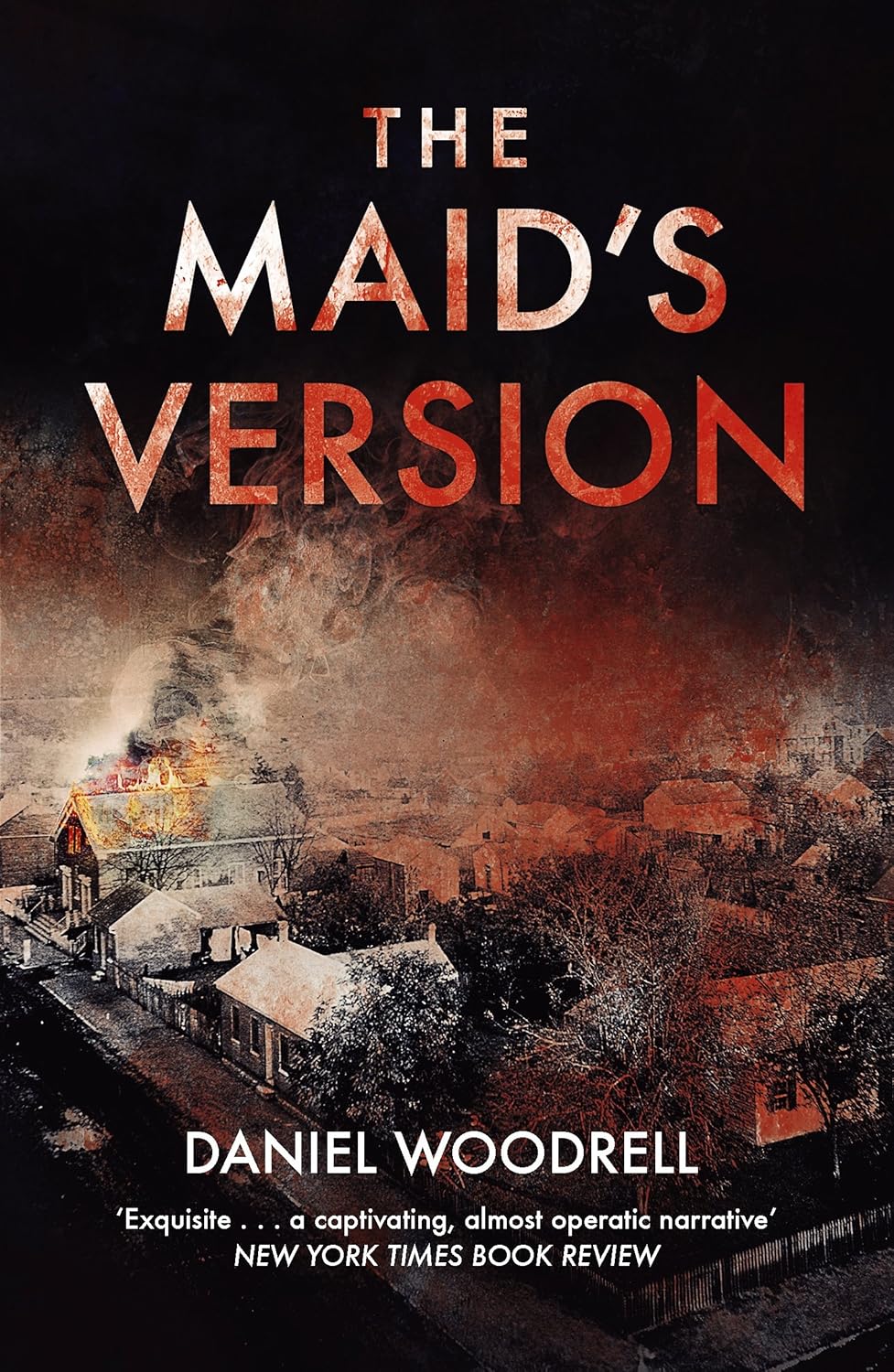あ~あ、やっぱりだよ…。つい先日、もう今年も最後だと思ってガラにもなく、良いお年を、とか吹いてたら舌の根も乾かんうちにもう一回やることになっちまった。まあ、そうなるかもという予感もあって、最後に言ってたけどさ…。
あ~あ、やっぱりだよ…。つい先日、もう今年も最後だと思ってガラにもなく、良いお年を、とか吹いてたら舌の根も乾かんうちにもう一回やることになっちまった。まあ、そうなるかもという予感もあって、最後に言ってたけどさ…。なんか最初からボヤキで始まって申し訳ないが、2025年のWanderland Book Awardの発表です。
前回、いつまでたっても発表が来ないんだよー、ボクがさぼってるんじゃないからねー、とお伝えし、12月15日の午後ぐらいに記事をアップした後、夜になって念のため検索し、あーやっぱまだだなあ、と思いつつちょっと 思い付きで、「Wonderland Book Award」の過去の検索履歴に「2025」を久し振りに足してみたところ、これまでなかった項目が見つかりそこを辿ってみると、Wonderland Book AwardやBizarroConの告知をやってるBizarro Centralの中に "Wonderland Award Winners 2025"というのが出てきました…。
一応記事の日付は11月17日になってるんだが、このサイトかなりしつこく見に行ってたけど今までそんなのなかったんで、多分11月17日に受賞作の方は決定したけど、発表するBizarroCon開催の方が決まらないんで、そっちの発表ができたら出す予定で準備的に書いといて下書き保存みたいな状況になってて、結局そっちの方の開催発表の方がどうにもならなくなったんで、この2~3日ぐらいのところでそれそのまま出しちゃったみたいな事情なんだと思う。なんか記事の方も前置き全然なくて、いきなり作家作品紹介するような形になってるし。いや、日付をごまかしてるとかじゃなくて、最後に保存した日にちが出てしまうシステムのところってだけなんだろうけど。なんだかこれを書き始めてる時点では、そういう情報をいち早く伝えてくれるLocus OnlineやFile 770の方でも記事が出て来てないぐらいなんで、ホントに昨日今日ぐらいのことかも?
まあこちらでなかなか伝えられなかった事情説明ではあるんだが、結構頑張ったんだろうけどうまく行かなかったそっちの人たちを責めるようになっちゃうのは申し訳ないと思うんで、とにかくご苦労さんでした、うまく行かなくて残念だったね、というぐらいで、何とか今年もアワードやってくれてありがとうとして、後はそちらの方をお伝えして行きます。
2025 Wanderland Book Award

短篇集部門
- The Expectant Mother’s Disinformation Handbook by Robert Guffey (Madness Heart Press)
- Inappropriate Toasts for All Occasions by Michael Allen Rose (Madness Heart Press)
- All Your Friends Are Here by M. Shaw (Tenebrous Press)
- Vile Visions: Volume Two by Riley Odell (Independently Published)
- God Is Wearing Black by Kelby Losack (Ugly Child)
短篇集部門受賞作品は、Robert Guffeyの『The Expectant Mother’s Disinformation Handbook』。
『妊婦のための偽情報ハンドブック』というタイトルのこの作品は、その名の通り妊産婦に関する医学的ガイドブックの形を取っており、Quantum Singularity Syndrome (量子特異点症候群)、Spontaneous Infant Combustion Syndrome (乳児自然発火症候群)、 Black Hole Syndrome (ブラックホール症候群)などの病気についてや、子宮内の胎児にインターネット接続を許可することへの危険性などについて、架空の専門家の脚注なども加え、科学的、専門的に解説しているというような作品。シェークスピアが妊娠を 発明したという驚くべき事実も語られているとか。
Robert GuffeyはCalifornia State Universityの英文科講師で、これまでにも10冊ぐらいの謎の著作があり、2022年の『Operation Mindfuck: QAnon and the Cult of Donald Trump』は、かのアラン・ムーアにも高く評価されているそう。
その他のノミネート作品について。
『Inappropriate Toasts for All Occasions』のMichael Allen Roseは、2022年に長編/中編部門を『Jurassichrist』で受賞の他、2023年の短編賞部門受賞作の『The Last 5 Minutes of the Human Race』の共作者でもある。
『All Your Friends Are Here』のM. Shawは、2023年に『One Hand to Hold, One Hand to Carve』で長編/中編部門を受賞している。
『Vile Visions: Volume Two』のRiley Odellについてはこれまでのノミネート歴など分からないのだが、Volume Twoとなっているように、2022年に『Vile Visions』も出ている。アンソロジーの編集なども手掛けている他、ニューロダイバーシティ(Neurodiversity、神経多様性)の社会的な理解と受容のための活動家でもあるそう。
『God Is Wearing Black』のKelby Losackは、これまで数作の著作はあるが、受賞歴は無しというところだが、最近Substackに自分の選んだ21世紀映画ベスト200というのを出してて、そこで三池崇史の『殺し屋1』を一位に挙げてたのを見た。今後に結構注目かも。

長編/中編部門
- Nympho Shark Fuck Frenzy by Susan Snyder and Christine Morgan (Madness Heart Press)
- Starlet by Danger Slater (Ghoulish Books)
- Apeship by Carlton Mellick III (Eraserhead Press)
- Reality But More Fun by Madeleine Swann (Nictitating Books)
- Kennel by Garrett Cook (Madness Heart Press)
長編/中編部門受賞作は、Christine MorganとSusan Snyderによる『Nympho Shark Fuck Frenzy』。
『色情狂のサメが狂乱的にファックする』というタイトルがすべてを語っておる、とかのエドワード・リー先生に言わしめた作品。リー先生によると聖書ほどの厚さがあるということで見てみたら、420ページの大長編。あー単純に日本の本 思い浮かべちゃダメだよ。翻訳されたら大体1.5倍かそれ以上になるから。
水族館で唯一の初の飼育の成功例となったホオジロザメ。水槽の中で威容を誇る彼だが、外の世界、同胞については何も知らない。唯一のものは彼にえさを与え育ててくれた美しい存在。だが、ある災害が彼をその閉ざされた安全な世界から、 外の世界へと強制的に解き放ち…。という作品らしい。
作者の一人、Christine Morganはスプラッタパンクアワードではもはや常連の一人なんだが、女性作家だというのを今の今まで知らなかった!申し訳ない…。そうだよな、クリスティンだもんな。根拠もなしにこのジャンルでは定番の とことんむさくるしい髭のおっさんを思い浮かべていた…。
多数の著作がある彼女だが、本業は精神科医で、最近30年のキャリアの末母親の介護のため離職し、現在は父親と共に砂漠地帯で次の展開に備えつつ隠遁しているということ。
共作のSusan Snyderもスプラッタパンクアワードで2度のノミネート歴がある他に、海洋学者としての一面も持ち、サメ映画についてやや皮肉に語ったノンフィクションの著作もあるそう(『Encyclopedia Sharksploitanica』(2021))。その他、 詩集も2冊出版。
その他のノミネート作品について。
『Starlet』のDanger Slaterは、2017年に『I Will Rot Without You』で長編/中編部門を受賞している。他にも多くの著作があり、割とユーモアのある感じのカバーが印象的。
『Apeship』のCarlton Mellick IIIは、もはやこのジャンルの重鎮といえる多くの著作のある作家。いつもながらこの人のカバーはいかす。
『Reality But More Fun』のMadeleine Swannもスプラッタパンクアワードのノミネート歴もあるそうなんだが、見つからなかった。ごめん。なんか名前見覚えあるんだがな?長編/中編部門ではそっちの活躍もある人が多い。
『Kennel』のGarrett Cookは、2014年に短篇集部門を『Time Pimp』で受賞している。経歴を見たら自著『Jimmy Plush, Teddy Bear Detective』のキャラによる「Mr. Plush, Detective」というのがミステリマガジンに載ったそうなんだがいつのだかわからん。この人も三池崇史のファンだそう。
* * *
そんなわけで、何とか年内にワンダーランドブックアワードの方も片付きました。なんか今年はスプラッタパンクの方も、両方ともそれぞれ事情は違えどバタバタしてたな。ワンダーランドブックアワードの方も、来年どうなるのかはちょっとわからんけど、少し説明してみただけでもこれだけ面白そうな作品を選べるんだから、何とか続けてもらいたいものだと願います。
スプラッタパンクアワードの方も大丈夫かなと思ってちょっと調べてみたら、来年のKillerconの開催はもう決まってるけど、これまでの8月から、来年は11月頭になるとか。なんかホラーを取り巻く状況とか変わって来てんのかな?悪い方じゃないといいけど。
多分一応アメリカって限定しといた方がいいのかと思うけど、その辺のホラーの状況って、音楽みたいなところに例えるとわかりやすいのではないかと思う。つまり、メジャーなJ-Pop的な部分がまずあり、スプラッタパンクやビザールフィクションみたいな部分は、 ロックだとかメタルとか、テクノやノイズといったところに位置するんだろうと思う。大体音楽とか昔からそういう形なんで、最近のものは聴かない年の人でも大体見当つくと思うけど。
女性にも人気のメジャーなベストセラー的なところすらほとんど入って来ない日本じゃ、その辺のところは本当に遠いところなんだろうと思う。なんか入ってきたらきたで、日本の実話怪談の方が怖い、日本の勝ちー!レベルに粗雑に 扱われるだけみたいなことになるんだろうけどね。
そういった手の届きにくいけど確実に面白いものがあるというところで、「『妊婦のための偽情報ハンドブック』を一位にしたのはまずかったネ」みたいなことを決して言い出さない、視野の狭い小手先の売れる売れないに振り回されずに優れた作品を 選び出してくれる場というのは本当に貴重だと思う。色々と苦しいところもあるんだろうが、両アワード共になるべく長く続いてこのジャンルの優れた作品を選び出して行ってもらえればと願うよ。
とりあえずスプラッタパンクアワードについては、今年12月31日のノミネート応募締め切りも告知されてるが、発表が11月となるとノミネート発表の時期も変わるのかも?とにかく2月ぐらいからはしつこくBrian Keeneのホームページをチェックしに行かねば。 そして秋ごろにはまた「Wonderland Book Award」を毎日のように検索してみよう。来年は順当に行けば、11月にどちらも発表となると結構大変そうだが、そこんところはもうハロウィン後のホラー祭りじゃい!と頑張れるといいですね。
前回書いたように、やっと当方でもいくらかこの辺でセレクトされたホラー作品を読み始めたが、なかなか書くまでの余裕が作れない。とりあえずはとにかく読んで積み重ねて行けば、こっちジャンルに関する視野も広がるんではないかと。来年には何とか少しずつでも書けるように努力しますです。
というわけで、今度こそ本当に今年最後です。最後だよな…?今度こそ、良いお年を。ではごきげんよう。
●関連記事
2024 ワンダーランド・ブック・アワード 受賞作品発表!過去(2008-2023)の受賞作一覧はこちら→